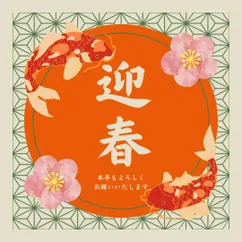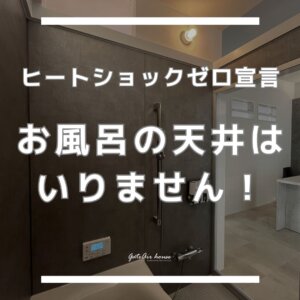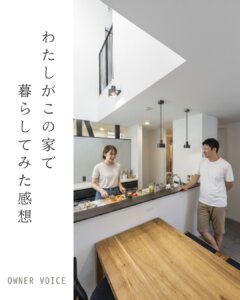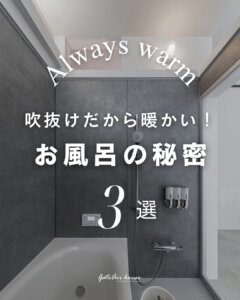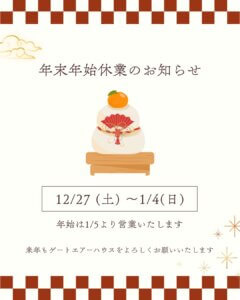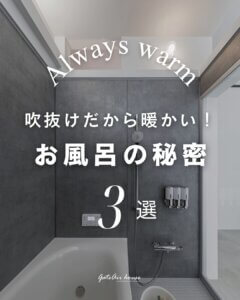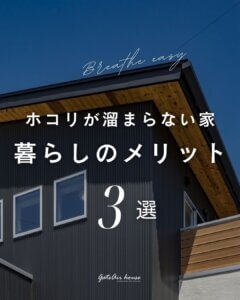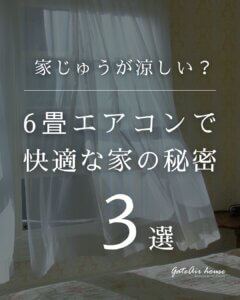地震に強い家のポイント3選!
はじめに
能登半島地震で被害に遭われた方々に謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご快復、ご復興を祈念致します。
この機会に今回は「地震に強い家のポイント3選」をお知らせいたします。
「地震に強い家を建てる」ということは、地震大国といわれている日本で長く住むためにはとても大切なことです。
実際に家づくりを検討して、弊社に来られるお客様も
「地震に強い家を建ててくれるのか」をとても重要視しています。
では、どうしたら地震に強い家になるのか。
基礎の強さ(ベタ基礎、立上り幅)
耐震性を高めるためにはやはり基礎が重要になります。どんなに強固な構造の家を建てても、基礎が強力でなければ地震に強い家とは言えません。
弊社では「ベタ基礎工法」で施工するだけでなく、建築基準法に基づいた基礎の立上り幅“12センチ”よりも分厚い“18センチ”で施工することで一般よりも高い基準で、安心・安全をご提供いたします。

構造の強さ(許容応力度計算による耐震等級3の取得)
次に壁の強さや部材の強さがとても重要となります。家の強度を判断するためには3つの方法があります。
①建築基準法の仕様規定
②品確法における性能表示計算
③建築基準法の構造計算
この3つの内、「①仕様規定」は耐震等級2以上の取得ができません。
耐震等級3を取得するには「②性能表示計算」もしくは「③構造計算」どちらかで計算・見当が必要となります。
では「②性能表示計算」と「③構造計算」の違いはなにか。それは時間とコストの差です。
「③構造計算」の中でも許容応力度計算は最も耐震性に優れた計算方法です。
各部材一つ一つの応力を計算し、隅々まで値を算出しているので最高レベルの地震対策をする場合は許容応力度計算が欠かせません。
しかしそれには時間とコストがかかってしまうため、多くのハウスメーカーや工務店は、性能表示計算によって設計をしているところがほとんどです。
同じ耐震等級3であっても構造計算(許容応力度計算)で建てられた家の方が明らかに強い家なのです。
弊社では一棟一棟許容応力度計算を行い家を建てています。
また基礎と同様に弊社では、一般的な柱よりも一回り太い柱を使用しています。柱が太くなるということは、それだけ家の強度が上がります。
制震ダンパーの導入
地震に強い家を建てるために、「1」「2」で耐震性を上げます。
ですがそれだけでは安心と言い切れません。
地震に強い家を建てるために欠かせないのが制振装置です。
弊社では“住友ゴム”の「MIRAIE」という制振ダンパーを採用しています。

耐震等級3相当の木造建築物に対して、震度7の相当の地震波を繰り返し入力し、
MIRAIE装着とMIRAIE非装着で、建物の上層と下層の揺れ幅(層間変位)を測定。
この結果、地震の揺れ幅を最大95%低減できることが実証されました
MIRAIEは、一度取り付ければ部品交換や点検などメンテナンスが不要。
効果は90年※持続するので、定期的なメンテナンス費用が発生しません。だからお孫さまの代まで安心。
※当社による促進劣化試験の結果より(高減衰ゴムダンパー部分において)
一度取り付ければ、お子様、お孫様の代まで安心が続きます。
まとめ
夢のマイホームを建てる時、目の見えないものにお金をかけるということに抵抗があるのはよくわかります。
ですが「家」は日々のご家族の命と財産を守る場です。
キッチンやお風呂などは古くなったら取り替えられますが、耐震性能は家の構造に係っている為、取り替えることはできません。
建ててから変えられない部分こそ徹底して安全対策をするべきだと思います。
そして是非、色々なハウスメーカーの「構造見学会」に参加してみてください。
家の中身を見られるのは、建てている最中だけです。
完成してしまってからでは見ることができません。
みることができなくなってしまう構造の部分が家づくりにとって一番重要です。
弊社は来月、構造見学会を開催します。
基礎、制振装置、断熱材などを実際に見ていただきながら、その場で気になることを質問していただけます。
お気軽にご参加くださいませ。
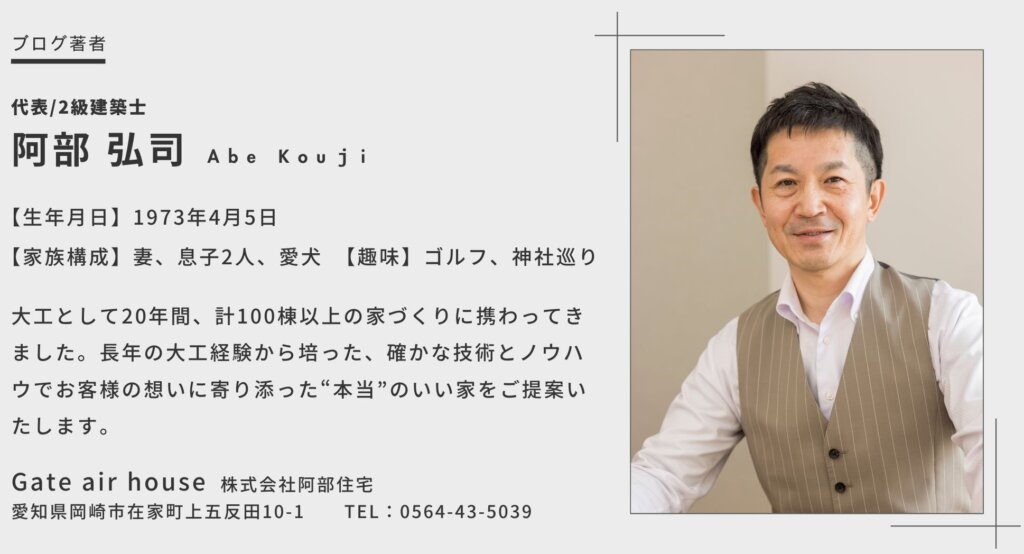
Gate air house 株式会社 阿部住宅
愛知県岡崎市在家町上五反田10-1
TEL:0564-43-5039